【PR】この記事には広告を含む場合があります。
最近はオーディオブックも気になるし、良い使い分け方を教えて!
そんなお悩みに、現役ライターがお答えします。
この記事の内容
◆オーディオブック歴:2019年〜
◆インタビューメディア「ひとびとのひび」編集長
◆販促制作会社1人経営者 & ライター
本を上手に使い分けると、大きく3つの効果が生まれます。
①お金のムダを防止
②ムダな本の置き場所を削減
③読書の時間を超効率化
本記事では、紙・電子書籍・オーディオブックの特徴を整理整頓し、賢い使い分け方を解説します。
あなたの読書ライフをアップデートできるはずですので、ぜひ最後までお付き合いください。
今すぐ使い分けを始めるべき3つの理由

3つの効果が生まれるのはなぜか?
①お金のムダを防止
②ムダな本の置き場所を削減
③読書の時間を超効率化
本によって「お得な買い方」「利用シーン」「保管場所」がそれぞれ違うからです。
| お得な買い方 | 利用シーン | 保管場所 | |
|---|---|---|---|
| 紙の本 | 中古、個人売買 | 自宅、通勤車内、休憩中 | 必要(本棚など) |
| 電子書籍 | Kindle版、他各社割引サービス | 外出先、休憩中、自宅 | 不要(データ) |
| オーディオブック | 無料体験、聴き放題、各社割引サービス | 家事中、移動中、運動中、就寝中、すき間時間 | 不要(データ) |
それぞれの特徴を最大限に活かす方法をひとつずつ解説します。
①お金のムダを防止
まずはお金の面から。
本を買う前に、以下の選択肢から考えないと損する可能性が高くなるばかりなので要注意です。
【紙の本】中古本は必ずチェック
◆Amazon
◆" target="_blank">楽天ブックス
◆自由テキスト" target="_blank">紀伊國屋書店
◆" target="_blank">U-NEXT
◆hont などなど
例えば、通販で紙の本を買うときは、中古本の出品者をまずチェックするのがテッパンです。
意外とキレイな中古本と出会えることも多いのでおすすめですよ。
ただ、中古本は発送に時間がかかるケースがあるので必ず確認しましょう。
【電子書籍】各社割引サービスを利用
◆Amazon
〈Kindle版、読み放題サービスUnlimited〉
◆楽天Kobo
〈100円、無料、〇〇%OFF〉
◆自由テキスト" target="_blank">紀伊國屋書店
〈特価セール、割引キャンペーン〉
◆" target="_blank">U-NEXT
〈キャンペーン、無料お試し版〉
◆hont
〈セール、クーポン〉 などなど
他にも、たくさんの「電子書籍販売サービス」や「割引サービス」があります。
その中でも、Amazonがおすすめです。
主な理由は、「Kindle版の割安感」「Kindle版の品揃え」「アプリの使いやすさ」。
アプリの使いやすさでは「紀伊國屋書店」も良いですが、Kindle版の割安感が優っています。
Amazonプライム会員なら配送料が無料なので、「家で読むなら紙の本」「持ち出したいならKindle版かオーディオブック」というように、選択肢が広がるのが大きなメリットです。
【オーディオブック】無料体験、聴き放題、割引キャンペーンを利用
オーディオブック最大のメリットは、無料体験ができること。
これが他の本と決定的に違うポイントです。
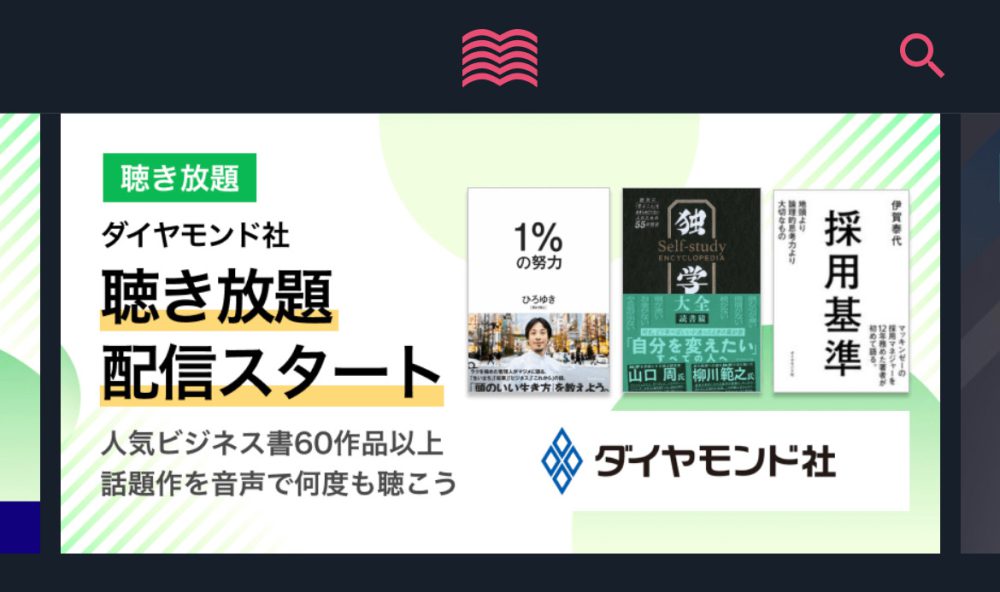

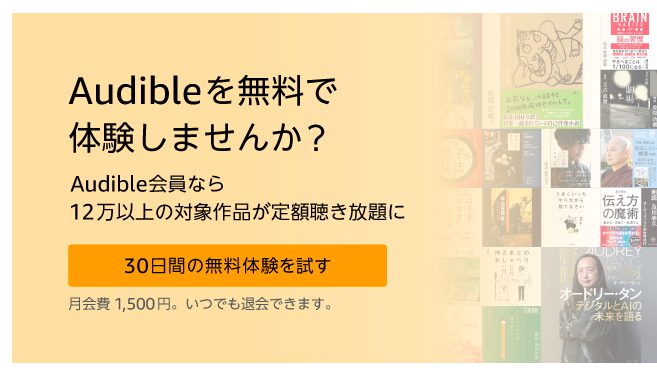
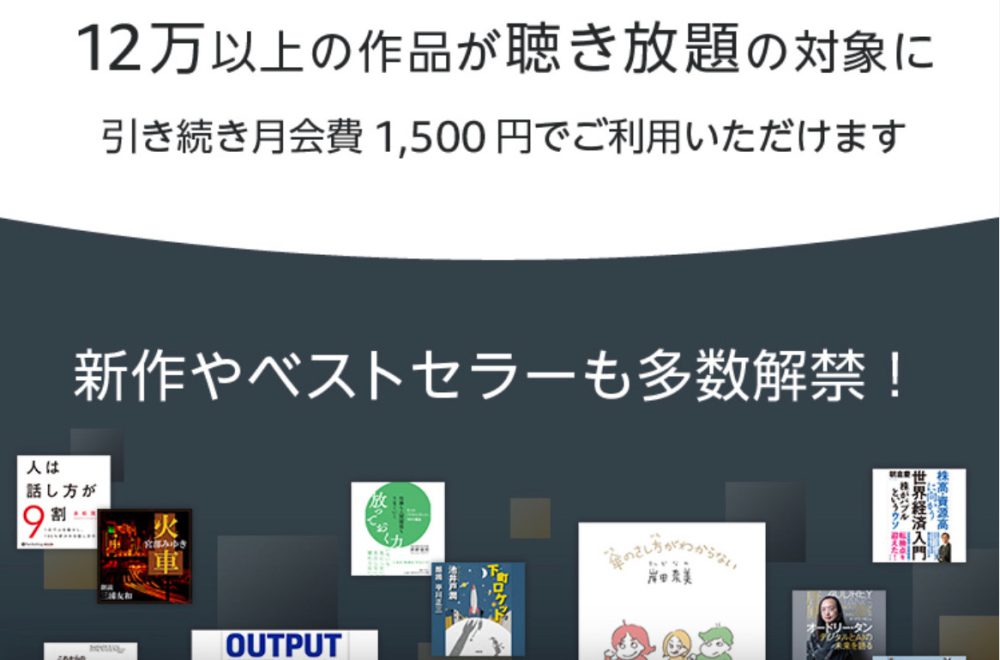
サブスクの聴き放題プランがあるのもオーディオブックの魅力。
使ったことがないから「とりあえず試してみたい」という方にはぴったりのサービスです。
オーディオブックのサービスもたくさんありますが、
「使いやすさ」「料金」「作品数」を考えても、上記のaudiobook.jpかaudibleがおすすめ。
私は「audible」の聴き放題をメインで利用しながら、欲しいビジネス書があれば「audiobook.jp」で単品購入しています。
>>Audible聴き放題の無料体験についてはこちら
②ムダな本の置き場所を削減
紙の書籍の最大の弱点は、ムダに場所をとること。
電子書籍やオーディオブックの利用を増やすことで、紙の本が減り、お部屋も本棚もすっきり。
本当に必要で、大切にしたい本だけ残せるので、スペースを有効利用できるってことです。
逆に、「電子書籍」や「オーディオブック」なら100冊でも1000冊でも持ち歩けて、いくら買ってもジャマになりません。
これ、実際やってみるとメチャクチャ素晴らしくて感動しますよ。
③読書の時間を超効率化
紙、電子書籍、オーディオブックの「利用シーン」や「タイミング」を上手に組み合わせることで、ムダなく、効率的な読書効果が生まれます。
例えば、オーディオブックなら次のような使い方が考えられます。
朝:家事中、通勤時間
午後:外出時
夜:帰宅時間、ジムでの運動中
こうしたすき間時間にオーディオブックを使いながら、「仕事の休憩時間」や「帰宅後」などに活字の本を組み込んでいく。
平日と休日で使い方を分けてみるのもおすすめです。
読書のマメ知識
紙の本、電子書籍、オーディオブックのメリット・デメリットを比較

「紙の本」「電子書籍」「オーディオブック」の特徴は、大きく2つに分けられます。
◆紙・電子書籍▷▷「活字読書」
◆オーディオブック▷▷「音声読書」
当たり前と思うかもしれませんが、この2つの決定的な違いは「目を使うかどうか」。
だから目で把握する活字の本は、「難しい内容の本」「ノウハウの実践」「資格取得の勉強」などにおすすめです。
逆に、以下のような本はオーディオブックと相性抜群ということです。
✔️ 「内容が分かりやすい本」
✔️ 「聴いていて楽しい本」
✔️ 「何度かループして覚えられれば良い本」
後ほど詳しく解説しますが、まずは「紙、電子書籍、オーディオブック」のデメリットから確認してみましょう。
デメリットを把握する
ひとつひとつ丁寧に見ていくと、やっぱりそれぞれにデメリットはありますね。
| デメリット | |
|---|---|
| 紙の本 | ・重い、持ち運びに不便 ・劣化する、保管場所が必要 ・寝転がって読みづらい ・明るくないと読めない |
| 電子書籍 | ・読後に売れない ・マーカーはできるが書き込めない ・全体のボリュームをつかみにくい |
| オーディオブック | ・難しい内容は聴き取りにくい ・図や表を見るのが面倒 ・集中していないと気が散りやすい |
そのデメリットを補い合うのも、使い分けの目的です。
特にネックとなるデメリットを把握しておきましょう。
✔️ 紙の本のデメリット
保管場所が必要なのはもちろんデメリット。
でも一番は、「動きながら読めない」「暗い部屋で読めない」こと。
電子書籍も動きながらはムリですが、画面が光るので暗い部屋でも読めますよね。
ただ、目が疲れるのは、紙も電子書籍も共通のデメリット。
このデメリットから解放してくれるのが、オーディオブックということです。
✔️ 電子書籍のデメリット
電子書籍の悲しい点は、本を見開きにできないので、全体を把握しにくいところ。
といっても、検索機能があるので、さほど困ることはありませんけどね。
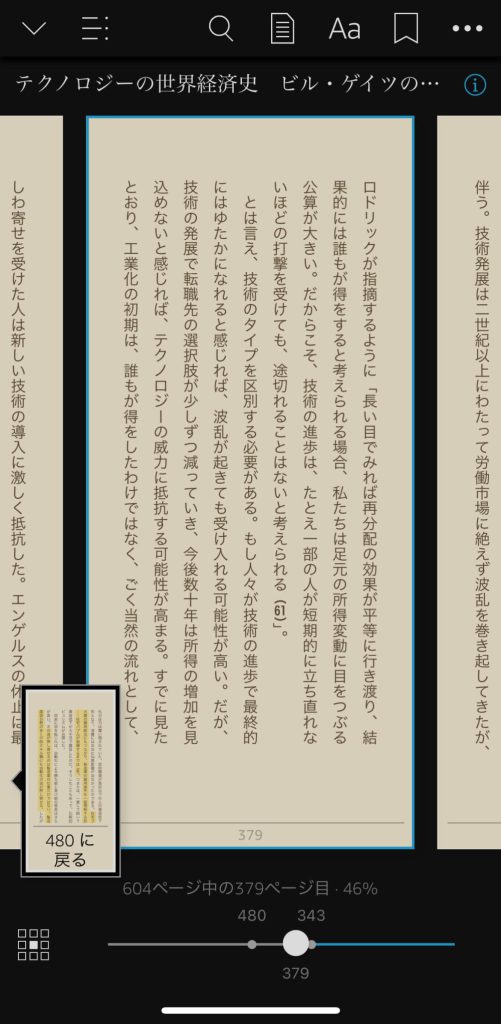
求めるページへ移動するのに、ワンアクション必要になるのがちょっと残念。。。
これは、紙の本にもオーディオブックにもないデメリットですね。
✔️ オーディオブックのデメリット
音声の読書は、内容や言葉づかいが難しいと、右から左へビュンビュン抜けていきます。
図表が多いと見るのが面倒なのも弱点です。
なのでビジネス・学術系は要注意。
紙の本でも、難しい本って一回じゃ頭に入りませんよね?
そう考えれば、驚くほどのデメリットでもありませんが。
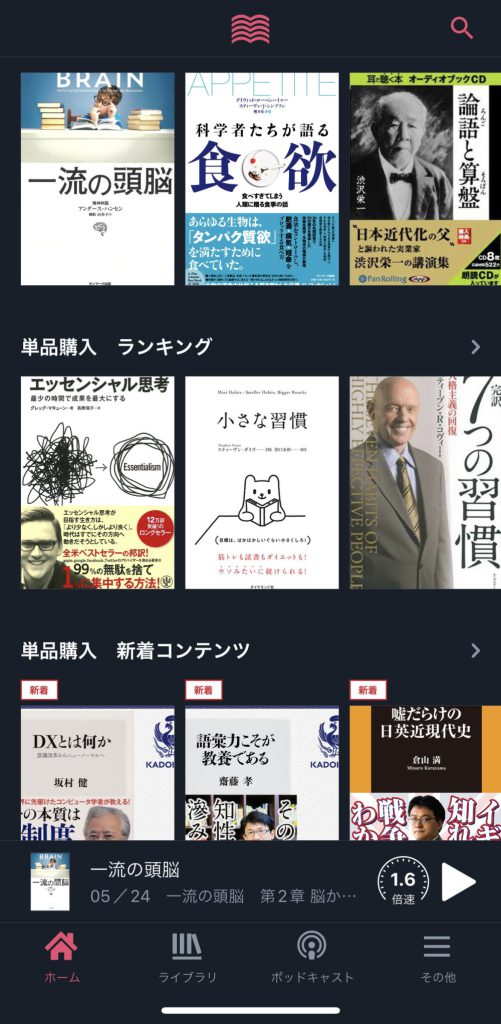
むしろオーディオブックは、何度もループして聴くことが苦にならないのが最大の強み。
速度を変えて聴きやすくすることもできるので、「何度か繰り返して頭に入ればいい」という本は、オーディオブックに向いています。
紙の本を何度も読み返すと片付けられないし、ずっと読み終わらない気がしますよね。
特に、赤文字部分のデメリットを避けたい場合ほど、使い分けが効果を発揮するんです。
| デメリット | |
|---|---|
| 紙の本 | ・かさばる、重い、持ち運びに不便 ・劣化する、保管場所が必要 ・寝転がって読みづらい ・明るくないと読めない |
| 電子書籍 | ・読後に売れない ・マーカーはできるが書き込めない ・全体のボリュームをつかみにくい |
| オーディオブック | ・難しい内容は聴き取りにくい ・図や表を見るのが面倒 ・集中していないと気が散りやすい |
これらを踏まえて、それぞれの本のメリットをチェックしてみましょう。
メリットを把握する
各本のメリットなんて、ふだんは真剣に考えたりしないので、この機会にチェックしてみましょう。
| メリット | |
|---|---|
| 紙の本 | ・全体のボリュームが分かりやすい ・マーカー、書き込みが自由 ・読後に中古本として売れる ・難しい字や専門用語、図表が見やすい |
| 電子書籍 | ・一瞬で買える、売り切れない ・何冊買っても場所をとらない ・便利な機能が多い(辞書、メモ、しおり、マーカーなど) ・難しい字や専門用語、図表が見やすい |
| オーディオブック | ・売れている人気作品が多い、聴き放題がある ・一瞬で買える、売り切れない ・何冊買っても場所をとらない ・移動中・運動中も使えて読書時間を確保しやすい ・目を閉じたまま読める、目が疲れない ・活字を読む必要がない、読書が苦手でもOK ・再生速度を調整して早く読める |
特にメリットとして把握しておきたいのが以下になります。
✔️ 紙の本のメリット
自由に書き込んだりできるのは紙の本ならでは。
ノウハウの実践や資格取得などの学びには特に最適です。
紙・電子書籍という活字の本は、難しい言葉や図表などを目で認識しながら内容を読めるのも特徴。
全体のボリュームを俯瞰して見られ、好きなところから読める自由さも特徴。
電子書籍やオーディオブックは、「もくじ」に表記されたページならタップして飛ぶことができます。
こうしたオーディオブックとの大きな違いがあるからこそ、使い分ける意味があるんです。
✔️ 電子書籍のメリット
「辞書、ハイライト機能(メモ)、しおり」は、特に便利。
電子書籍はマーカーを引いたところもしおりと同じ機能を持ち、一覧で見ることができます。
後で振り返り用として使えるので、かなり実用的です。
▷こちらはAmazon Kindleのメモ(ハイライト機能)の画面
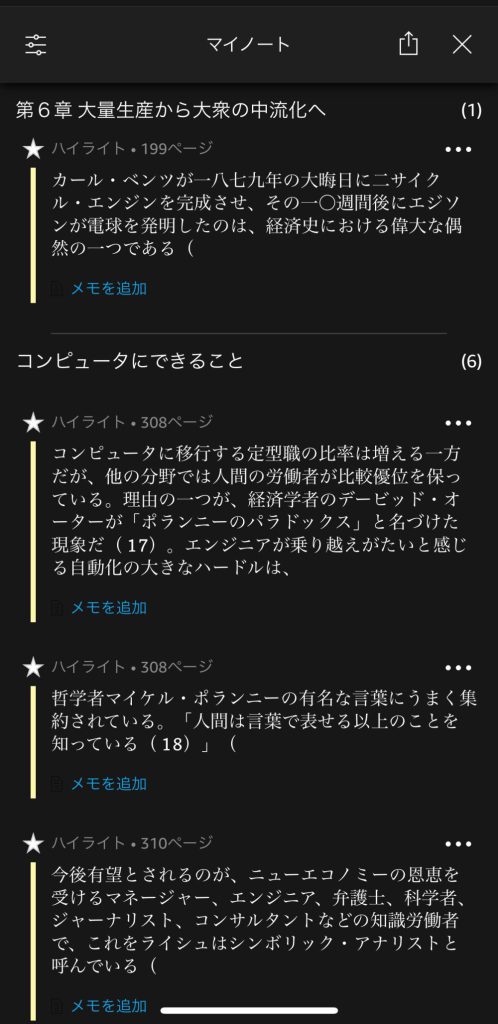
本文にマーカーを引くと、しおりとして記憶されると同時にクラウドに保存され「マイノート」で一覧として見ることができます。(PCの場合はAmazonの「notebook」ページ)
使いこなすほど、他の本との使い分け効果も増してきます。
✔️ オーディオブックのメリット
移動中だけでなく、屋内で家事中にも有効。
ワイヤレスイヤホンで聴けば洗い物や掃除機の音も気にせず読書できます。
これってかなり画期的ですよね。
明らかに、活字の本ではできない読書だけに、利用価値も高いんです。
そうした利用価値が活かされるのが、以下のような作品です。
✔️ 「内容が分かりやすい本」
✔️ 「聴いていて楽しい本」
✔️ 「何度かループして覚えられれば良い本」
まとめると、特にメリットとして活かしたいのは赤文字部分ということですね。
| メリット | |
|---|---|
| 紙の本 | ・全体のボリュームが分かりやすい ・マーカー、書き込みが自由 ・読後に中古本として売れる ・難しい字や専門用語、図表が見やすい |
| 電子書籍 | ・一瞬で買える、売り切れない ・何冊買っても場所をとらない ・便利な機能が多い(辞書、メモ、しおり、マーカーなど) ・難しい字や専門用語、図表が見やすい |
| オーディオブック | ・売れている人気作品が多い ・移動中・運動中も使えて読書時間を確保しやすい ・目を閉じたまま読める、目が疲れない ・活字を読む必要がない、読書が苦手でもOK ・再生速度を調整して早く読める |
ちなみに、2大オーディオブックアプリ「audiobook.jp」と「audible」は以下のような特徴があります。
◆オトバンクaudiobook.jp:世界でヒットしたような高価格帯のビジネス本が多い。
◆Amazon audible:小説や文学、自己啓発、ポッドキャストなどコンテンツが幅広い。
興味のある方は、ぜひ無料体験から触れてみることをおすすめします。
▷お得な無料体験の方法は【オーディオブック始めるなら】audiobook.jp+audible=44日間聴き放題無料体験からで解説しています
【おすすめ】紙の本、電子書籍、オーディオブックの使い分け例
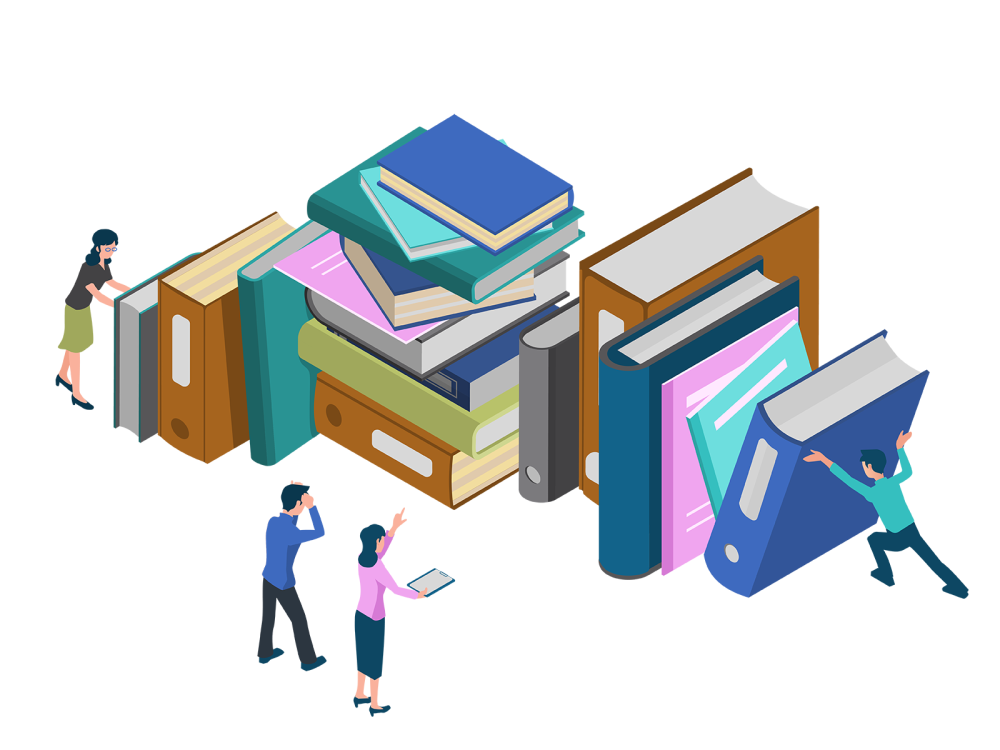
使い分けを考えるうえで、代表的な例と考え方をまとめました。
これが全てではないですが、よくあるケースですのでぜひ参考にしてください。
| 目的 | 利用シーン | |
|---|---|---|
| 紙の本 | ノウハウを実践・資格取得の勉強をしたい 中古本で安く買いたい コレクションしたい | 自宅(持ち運び不便) |
| 電子書籍 | Kindle版で安く買いたい 本を整理したい | 外出先、休憩中、自宅 |
| オーディオブック | ラクして頭に入れたい すき間時間に読書したい | 家事中、移動中、運動中、就寝中 |
以上を踏まえて、特に分かりやすい代表例を次でご紹介します。
こんなときは、紙の本がおすすめ
何かのノウハウを実践したいときは、本をそばにおいてひたすら作業したり、気になったことをメモしたりしやすい本がベスト。
それが最もしやすいのは「紙の本」ですよね。
実践的な本は、将来のためにも目の届く場所に保管しておきたいケースが多くなります。
単純にコレクションしておきたい本も、やっぱり紙ですよね。
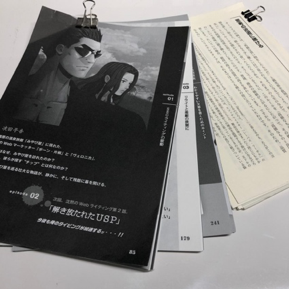
繰り返し見て覚えたいときはおすすめですよ。(モッタイナイと思う人以外には)
こんなときは、電子書籍がおすすめ
本棚の整理だけなら、オーディオブックもおすすめです。
でも、お得に買うとなると古本かKindle版。
本棚の整理もお得な購入も、両方満たしたいなら電子書籍ですね。
もちろん、何冊でもデバイス1つで持ち運べるので荷物も減らせます。
こんなときは、オーディオブックがおすすめ
オーディオブックの一番の強みは、すでに触れましたが、読書できないはずの時間を読書時間にしてしまうこと。
紙の本も電子書籍も、動きながら読むことはできませんよね?
しかもある程度まとまった時間がないと、読もうというスイッチも入りにくいもの。
でもオーディオブックは、移動中やお散歩中のほんのすき間時間も読書の時間に変えてくれます。
基本は「ながら読書」でループ再生しながら頭に入れるので、楽ちんです。
いかがだったでしょうか?
あなたなりの使い分けに、ぜひ実践してみてください。
オーディオブックと相性の良い書籍はコレ

参考までに、オーディオブックを使っていない方のために補足しておきます。
基本的に、本として読みやすく、やさしい語り口の文章は、音声でも聴きやすいものです。
そのイメージを基準にすれば、OKです。
小説、自己啓発、エッセイは聴きやすい代表例
例えば、以下のようなタイプの本ですね。(リンク先は" target="_blank" rel="noreferrer noopener">オトバンク社のaudiobook.jpです)
◆堀江貴文「ゼロ なにもない自分に小さなイチを足していく」
◆水野学「センスは知識からはじまる」
◆橘玲「幸福の資本論」
◆山崎元「学校では教えてくれないお金の授業」
◆デイル・ドーテン「仕事は楽しいかね?」
そもそも読者に話しかけるような文章で構成されているので、聴いていて違和感がありません。
耳元で朗読されている感じが、心地よくスーッと入ってきます。
※すべて実際に聴いたうえで紹介しているのでご安心ください。
慣れてきたらぜひ幅広く試してみてください。
歴史を語りで聴く効果についてはこちら
>>【歴史を聴こう】硫黄島の英霊から知る戦争の真実<音声読書で青山繁晴作品に学ぶ>
難しいのは外国語訳や専門用語連発系
外国語を和訳した学術系の本。
言い回しが分かりにくく、ついていけない場合があります。
◆ユヴァル・ノア・ハラリ「21世紀の人類のための21の思考 21 Lessons」 など
聴いてすぐ活字が浮かばないと、考えているうちに進んでいってしまうからです。
あまり大きな声で宣伝するのも気が引けるので一つにさせていただきました。
誤解のないように補足しますが、本としてダメと言っているんじゃありません。
オーディオブックには向かないという意味です。
オーディオブックは試聴できるので賢く利用しましょうね。
≪ 今なら14日間無料で聴き放題 ≫
\ 今なら30日間無料で聴き放題 /
【おまけ】意味不明なチマタの説を実体験から論破
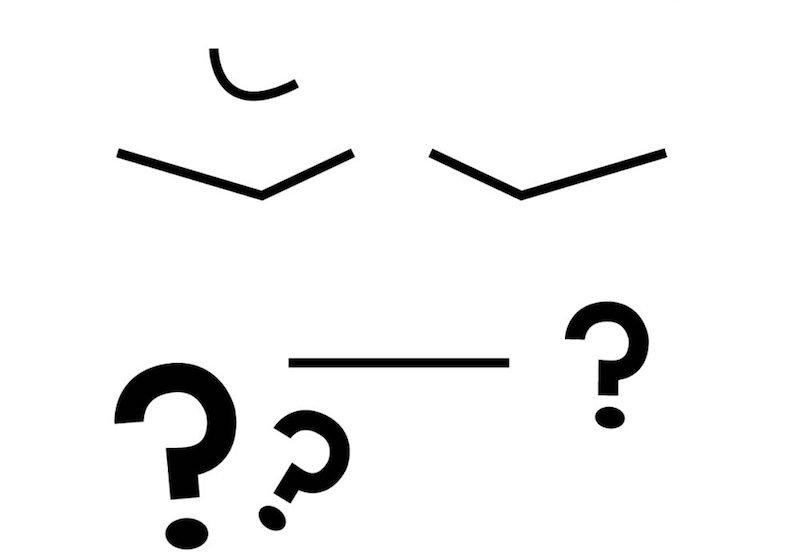
ネットでよく見かける、本についてのちょっとおかしな理屈。
それについても、私の実体験から検証してみましょう。
「読むのが早い」=電子書籍??
現状ではあてにならない説ですね。
そういう報告もありますが、そうでない実験データも見られるからです。
例えば、「随筆文」では紙の方が読むのが早いが、「説明文」では電子書籍の方が早かったというデータもあります。
※出典:情報処理学会研究報告「表示媒体が文章理解と記憶に及ぼす影響-電子書籍端末と紙媒体の比較-」
根拠のあやしい説は無視しましょう。
それより、読むときの集中力の方がよっぽど大事ですよ。
それに、電子書籍は読む端末によってもかなり違いがあります。
「スマホのKindleアプリ」は快適ですが、「Kindle電子書籍リーダー」だと動きがモッサイ・・・。
私は「Kindleペーパーホワイト」も持っていますが、すっかり「スマホ(iPhone)のKindleアプリ派です。
「Kindleペーパーホワイト」は目にやさしいことくらいしか利点を感じていませんね。
「何度も読み返す本」=紙の本??
ちょっと強引。
電子書籍でも読み返しは苦じゃないし、オーディオブックなら何度も聴くのは楽勝です。
しいて言えば、紙の本はデータが飛ぶリスクがないので何度も読むのに安心、という言い方はできますね。
「新しい本」「一回しか読まない本」=電子書籍
という人もいます。
ですが、「新しい本」だって好きになったら何度も読みますよね?
「一回しか読まない本」なんて、買う前に決められるワケない。
なので、これらを理由に使い分けを決めるのはやめましょう。
「本全体を暗記したい」=紙の本??
これも内容が分かっているなら別ですが、やはり買う前にそんなこと判断しようがありません。
「部分的に読み返して暗記したい本」=電子書籍
という論調も目にしますが、ちょっと論拠が乏しすぎますね。
そもそも、本全体を暗記なんてムリ・・・天才か!
本の特定のポイントを読み返して覚えるなら、オーディオブックは最適です。
私はよく「ブックマーク」したところだけリピートして学習に使っています。
【まとめ】ゴールは読書じゃない、情報の記憶だ!
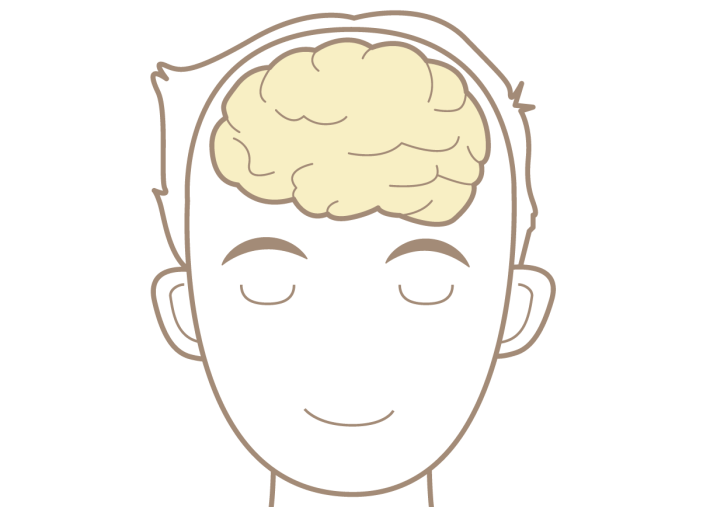
長くなってしまってすいません。。。
最初に伝えましたが、
本当のゴールは読書じゃなく頭に入れること。そして整理整頓です。
使い分けは、それを最大限しやすくする方法です。
そして、使い分けの基本はいたってシンプル。
| 目的 | 利用シーン | |
|---|---|---|
| 紙の本 | ノウハウを実践・資格取得の勉強をしたい 中古本で安く買いたい コレクションしたい | 自宅、通勤中、休憩中 |
| 電子書籍 | Kindle版で安く買いたい 本棚を整理したい | 外出先、休憩中、自宅 |
| オーディオブック | ラクして頭に入れたい すき間時間に読書したい 本棚を整理したい | 家事中、移動中、運動中、就寝中、すき間時間 |
まずは本を読む「目的」「利用シーン」をはっきりさせて、それに合わせたジャンルの本を選べばOKです。
あとは、「紙の中古本」「電子書籍の特典」「オーディオブックの聴き放題」など、どの本にもお得な買い方があることだけ忘れないでくださいね。
▷お得な無料体験の方法は【オーディオブック始めるなら】audiobook.jp+audible=44日間聴き放題無料体験からで解説しています
▷おすすめの使い方については【ライター流オーディオブック術】audiobook.jpとaudibleの賢い使い方で解説しています
◆自分の知らない経験をたくさんしている人の経験談や知識を与えてもらえる
◆ぶっとんだ想像力の持ち主が考え抜いて作り出した物語を楽しめる
それが本の魅力であり、読書の意味だと私は信じています。
ぜひあなたも、時間の許す限りいろんな本を通じて人生を豊かにしてください。
今回は以上となります。
最後までご覧いただきありがとうございます!
▷オーディオブックの脳科学的効果については【オーディオブックと脳の意外な関係】賢く読書したい人ほど効果あり〈おすすめの本も紹介〉で解説しています



コメントはこちら
コメントを投稿するにはログインしてください。