<インタビュー初心者からよく質問されること>
✔️ 「取材案件発生!え〜と、何からはじめるべき?」
✔️ 「取材で一番大事なことって?」
✔️ 「良い質問を考えるには?」
・・・みたいな。あなたも、そう考えそうですか?
確かに取材なんて、自分が担当することにならなきゃ深く考えることってないんですよね。私もそうでした。
直前になって・・・「そろそろちゃんと考えとかないとヤバくない?」「実際、ちゃんと話してくれなかったらどうしよう?」なんてことばかりループしてたりして。
本番が近づくほど、良いイメージが持てなくなるばかり。。。
いっ、胃が痛・・重い・・・
今もそんな状態になっている人、いるんじゃないでしょうか?
取材で合格点をたたき出すには、とにかく事前の準備にこだわるしかありません!
そんなこと言われたって、何から手を付ければいいか分からないっつーの!
というあなたのために、「企業の経営者」「芸能人」「教員」「ビジネスマン」「学生」さまざまな方に取材を行ってきた私が、誰でも合格点に到達できる準備のイロハを伝授します。
全部読んでいただけたら、安心しすぎちゃうかもしれませんが、ぜひ最後までお付き合いください!
◆インタビューメディア「ひとびとのひび」編集長
◆販促制作会社経営者&ライターで
自信なんかもてなくても取材を楽しむ方法はこちら
>>【取材歴10年ライター】インタビューって怖い?!楽しい学びにする7つの基本
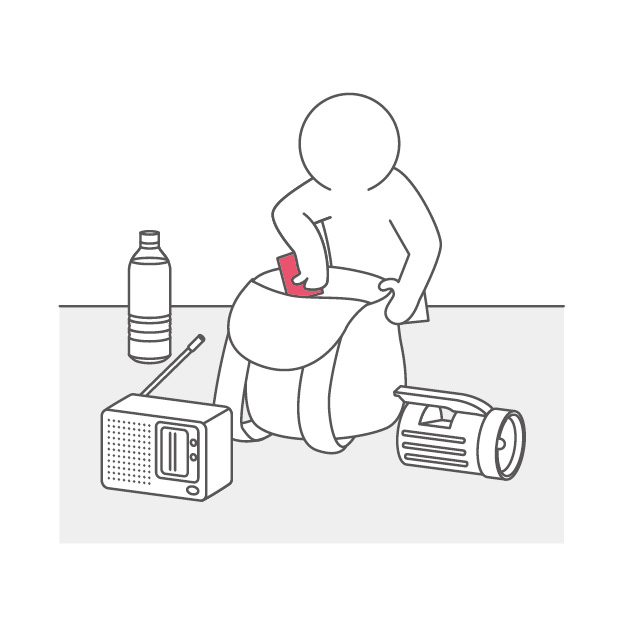
とにかく一番大事なのは、行く前の準備!
はっきり言ってこの準備で取材の成功の8割は決まります。
なぜなら本番はせいぜい1〜2時間程度。
キホンは準備したことを実践するだけ。その結果を原稿にまとめるだけ。
ですから、すべては準備の度合いで決まってしまうのです。
『失敗した〜!』と思ったら、それは結局、準備不足に他なりません。
必ずそこにいきつきます。
『思ったようにしゃべれなかった』のも、『頭が真っ白になっちゃた』のも、そういうこと。
そして、ゴールは取材を終えることでも原稿を上げることでもありません。
次の取材につながることがゴールです。
ってことで早速、準備不足にならないためのポイントを伝授していきましょう!
どんな取材も、基本は人と人の交流。実は、なにより大切なのは「笑顔」と「挨拶」です。
楽しく学ばせてもらう姿勢をもって明るくのぞめば、大きな失敗をすることはありません。
実戦でどんどんキャリアを積んで、未来のあなたの道をつくっていきましょう。
▷【ランサーズ】日本最大級のお仕事発注サイト!
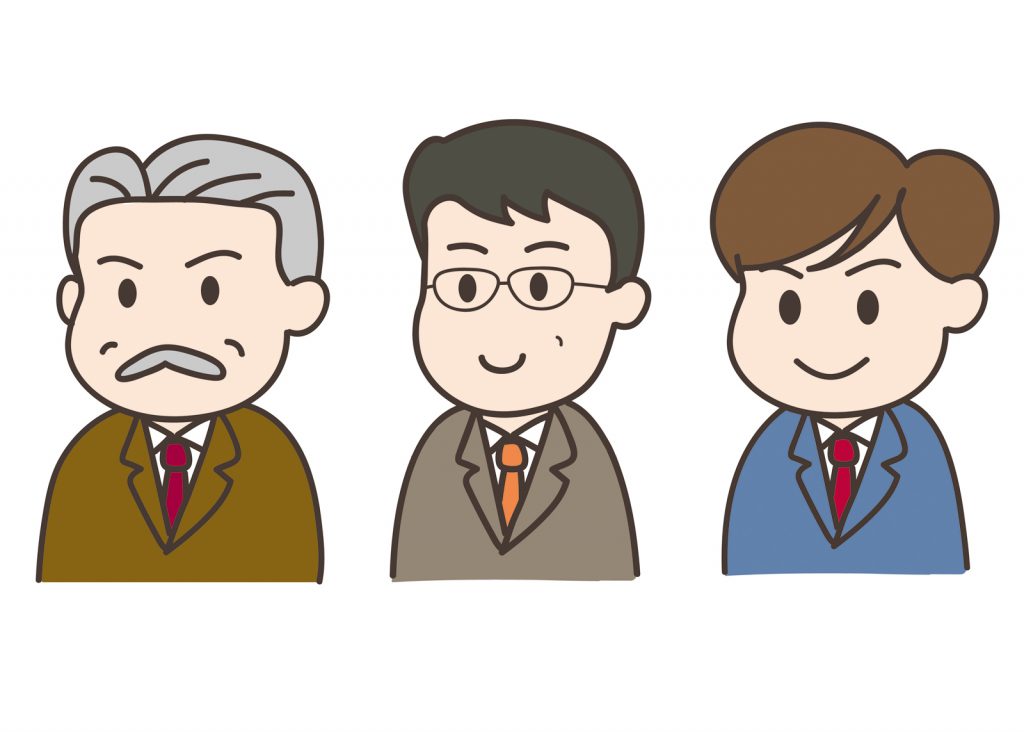
取材にはいろんな形があることをご存知か?
たとえば・・・
目的:
「会社・お店の紹介」「事業内容・プロジェクトの紹介」「社員の紹介」「導入事例の紹介」・・
対象者:
「社員・店員」「経営者・役員・管理職」「学生・教員」「医師など専門職」・・
設定:
「マンツーマン」「対談形式」「鼎談(ていだん・3人トーク)形式」「座談会」・・
などなど。
このように「目的」、「対象者」、「設定」によって、準備の仕方にも少なからず違いが生じます。
今回は、『ある企業の新プロジェクトについて一人の社員に話を伺う』想定で進めてみたいと思います。
では、レッツゴー!

取材の準備ってそんな大切?何すりゃいいの?
なんて思っている方のために。
ここからは、「来週、自分が取材に行くとしたら?」と、リアルに想像しながら読み進めてみてください。
まず、事前にやるべき6つのポイントをまとめました。
①『アポイント』
②『対象の周辺情報の確認』
③『目的の整理』
④『原稿の構成の整理』
⑤『質問の整理』
⑥『現場を想定したシミュレーション』
6つは多いですか?
でも、まともな取材にしたかったら、最低限このくらいはやってから当日にのぞんでください。
逆に言えば、これさえやっておけばまず大丈夫という6つのポイントでもあります。
では、1つずつチェックしていきましょう。
①アポイント

◇取材対象者へ取材の依頼:
企画主旨や取材目的をきちんと伝えたうえで、交渉・合意を獲得する。
もちろん、最初に報酬についてもきちんと交渉しておきましょう。これはマナーでもありますね。
◇対象者との事前確認:
対象者や企業の顧客・業務への迷惑を最小限に抑えられる日時(時間帯)、場所、人数、所要時間など詳細を提案・交渉・確認しておく。
◇必要資材・金額確認:
対象者への報酬だけでなく、持ち込むべきもの or 不要なものの確認、経費の発生の可能性やその金額などを確認しておく。
お料理や作品などについての取材・撮影をする場合などは、完成形を用意するための経費も想定しておきましょう。基本的には、取材を依頼するこちら側の出費になりますね。
・・・などなど。
ただし、アポ取りは取材者が直接やるケースは多くないです。
「もし必要になったとしたら」というつもりで目を通してもらえればOKです。
※ここからはアポ取りが済んだ設定で進めていきます。
②『対象の周辺情報の確認』
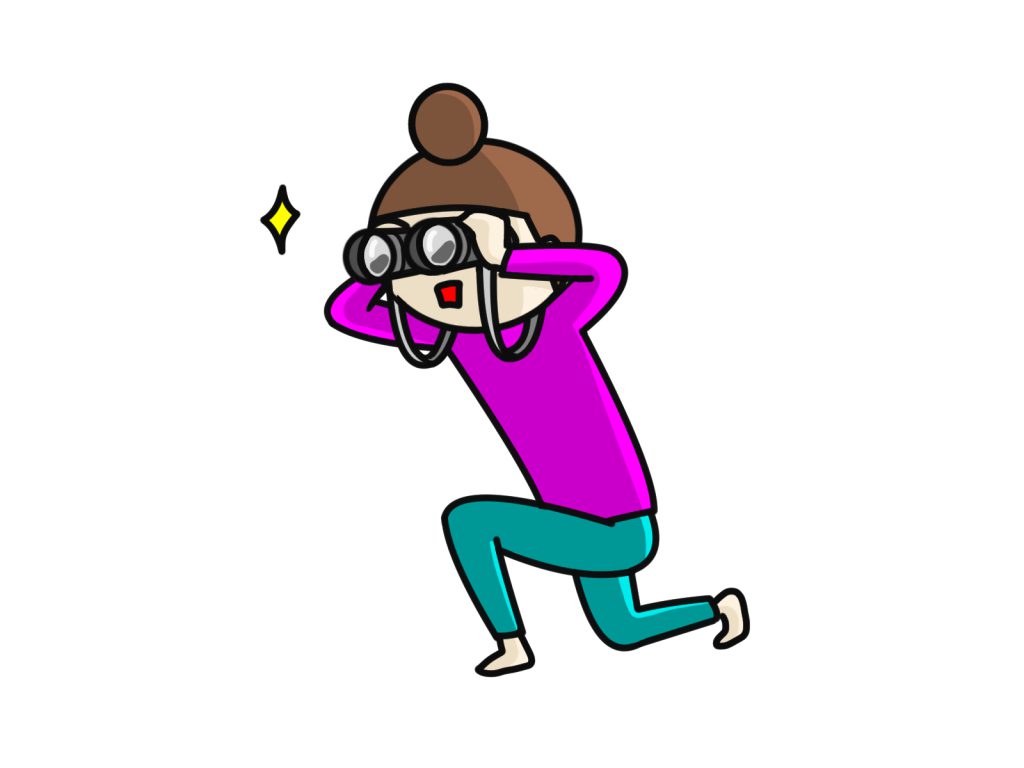
そもそも、取材をさせていただくうえで、相手のことを知らないというのは単純に失礼です。
相手は日常の業務やスケジュールを変更して、時には普段とは無縁の場所まで移動してインタビューに『協力してくれる』のですから、相手のことを一通り知ったうえで臨むのは『最低限の礼儀』だと考えてください。
そこで、
◎取材対象となる相手や企業などの背景・経歴・現在(企業情報、関連企業、競合他社)の情報をとにかく調べましょう。
→とにかく『知っていること』が『理解』につながり、『質問のきっかけ』を生んでくれます。
◎過去の取材記事、プロジェクト関連記事、採用関係の案件ならSNS情報や企業に関する口コミ情報なども参考になりますのでチェックしておきましょう。
→大手企業や人気ショップなどは取材経験も豊富な例が多いので、それに目を通さずに取材に行くのは失敗や失礼に直結する可能性が高いです。
恐いですよ〜
③目的の整理

前述した「目的」によって、取材の方法や準備の仕方は変わります。
より具体的に取材の成功をイメージするためにも、
『何を聞き出すための取材なのか』
『どんな結論にしたいのか』
それによって
『誰に何を感じてもらうための取材なのか』を事前に明確にしておく必要があります。
『誰に、何を、どう伝えるために、この取材をするんだっけ?』
『この取材を通じて、発信すべき・感じさせるべきメッセージは?』
ここがブレていたり、チームで共有できていなかったりすると絶対に良い取材はできません。
逆を言えば、ここさえしっかり固まっていれば、大きくブレたり失敗することもありません。
たとえば、
『新たな取引先となる企業』に、
『システム会社の熱い思い・身につくスキルの高さ』を伝え、
『未来の社会構造を本気で変えようとしている』経営姿勢をアピールする。
とか
できるだけ
『OJTの安心感や任されるプロジェクトの具体例』を盛り込み、
『学生たちに自分事のように入社後のイメージ』をリアルに感じさせたい。
とか
そして、読み終わったときに
『いままで以上の興味・好意』を抱かせ、
『積極的に接点を持とう』という行動につなげたい。
・・・みたいな。
大事ですよ〜
④原稿の構成の整理

ここで大事なのは、『理想的な原稿の形」と『最低限の原稿の形』の両方を想像しておくことです。
残念ながら、取材では、必ずしも理想的な答えをもらえるとは限らないからです。
相手がどんなしゃべりの達人でも、そんな都合良く完璧な答えがもらえるなんて、まぁあり得ません。
『最低限の原稿形』とするために必要なこと。
そうならないために、少しでもプラスすべき要素とは何か?
これらも合わせて頭に思い描いておくことを忘れないようにしましょう。
その掘り下げ方が、良い質問や現場の雰囲気に思いっきり直結しますので、できるだけ明確にしておくのです。
重要ですよ〜
⑤質問の整理(インタビュアーが作るのが理想)

「原稿の整理」でつかんだ流れをイメージしながら、「質問の整理」へ移りましょう。
基本的に、原稿の流れと質問の流れは相関します。当たり前の話です。
ゴールとして目指したい原稿の『起・承・転・結』を考えるとき、それぞれの内容はそのまま質問の答えで構成されるからです。
『起』:そもそものコトの始まり
『承』:物語が発展する前のフリ
『転』:物語の山場、本題、見えた苦労(課題)
『結』:物語の結末、成果、オチ、未来の展望
まさに、質問の順番そのものですよね。
聞きたいことは、書きたい内容とリンクするのです。
だからこそ、書きたい内容、伝えたい目的がブレていると、質問がブレるのです。
要するに質問内容とは・・・
◆『最低限の原稿の形』のために聞くべきこと
= 『マストの質問]』
◆『理想的な原稿の形』のために聞くべきこと
= 『付加価値となるプラスαの質問』
だと思ってください。
この際の質問事項は、できるだけインタビュアーでありライターである自分自身でつくるようにしましょう。
原稿を書く人の意向を理解していない人が作成すると、前述の『起・承・転・結』の理解のない質問になりがちです。
これはメチャクチャ原稿にしづらい。
なにより、理想的な『起・承・転・結』をシミュレーションする意味において、ライター自身がつくるのは理想的であり、当然です。

★同じデータを先に先方と共有しておき、プリントしたものに個人的なメモを入れている想定です。
そして、シミュレーションした際に浮かんだ質問などは質問票に補足でメモしておくと良いでしょう。
お話を伺いながら、物足りなければメモを見ながら質問できるようにしておくのは、『理想的な原稿の形』を目指す上でもかなり有効です。
当日、現場へ行くまでの間に、思い浮かんで使えそうだと思ったことは、メモしておくことをオススメします。
『念のためにメモっといたことが、こんな嬉しいコメントにつながるなんて!』
みたいなことが実際にあったりしますから、質問内容に関しては貪欲に準備しておきましょう。
⑥現場を想定したシミュレーション

「質問の整理」が終わったら、それをもとに「現場を想定したシミュレーション」をしておきましょう。
別に、リハーサルってほど深刻な話じゃありません。
ただ、質問を口に出してみることで、聞き方の不自然さや前後の流れの違和感などに気づくことができます。
違和感を訂正すると、もっと核心に迫れるような質問や効率的な流れが浮かんできたりすることも良くあります。
そして、もうひとつ。
足りない質問や想定外の答えに気づく効果もあります。
書面にしておくべき質問と、自分のメモとして控えておきたい質問の整理がつくのです。
なおかつ
『こんな答えが返ってきちゃったらどうしよう?』
『違う意味に聞こえそうかも・・・』
といった不安要素にも気づくことができます。
それによって、客観的に当日をシミュレーションでき、より適切でムダのない質問を用意できるというワケです。
【ご注意!】意外と忘れがちなのが、取材対象者から名刺をもらうこと。
忙しい社員の方や営業中で慌ただしい店内スタッフだったりすると、対象者が名刺を忘れてきたり、自分がもらうタイミングを損ねることって、結構なアルアルです。
後日、原稿を書く際に対象者の肩書きやフルネームが分からなくて困ってしまうことになるので、取材時は必ず名刺交換をすることを忘れないようにしましょう!
まとめ
ザッと駆け足になりましたが、以上が取材にのぞむ際の事前準備についてです。
①『アポイント』
②『対象の周辺情報の確認』
③『目的の整理』
④『原稿の構成の整理』
⑤『質問の整理』
⑥『現場でのシミュレーション』
これらを忘れずにきちんと備えておくことで、取材本番はかなりスムーズに進行できます。
まさに、『成功の8割は準備で決まる』の理由が分かるはずです。
もちろん、「現場でのインタビューのコツ」や「原稿を書く上でのポイント」、「マストなアイテム」など、アドバイスしたいことはたくさんありますので、後日また個別にご紹介できればと思います!
最後までご覧いただきありがとうございました!
▷取材を『おいしい対話と経験の時間にする方法』はこちらの記事でご紹介しています
▷弊社運営サイト取材例もよろしければ参考にご覧ください!
『ひとびとのひび』仕事紹介はこちら



コメントはこちら
コメントを投稿するにはログインしてください。